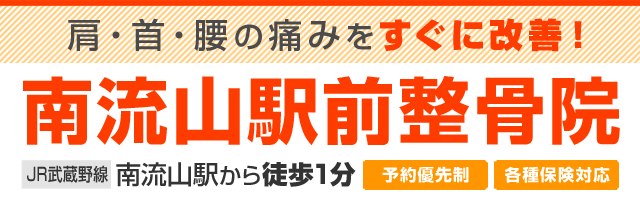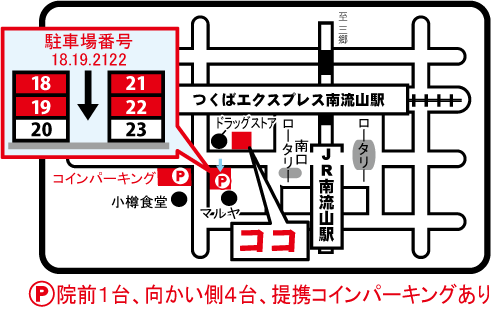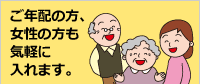巻き肩


こんなお悩みはありませんか?

スマホやパソコンを使う時間が長く、前かがみの姿勢で肩が凝りやすく、首が前に出て猫背になってしまう
真っすぐ立ったとき、肘が体の外側を向いていたり、手の甲が前を向いている
横向きで寝ることが多い
背中が丸くなり、姿勢が悪く見えてしまう
首が前に出て、首に負担を感じることがある
首への負担が続き、頭痛やめまいを感じることがある
巻き肩について知っておくべきこと

巻き肩は、姿勢の乱れが見られる状態です。見た目としては背中が丸くなり、首が前に出てしまいます。巻き肩になると猫背になりやすく、頭痛やめまいを引き起こすことがあります。
スマートフォンやパソコンを長時間使用することで、胸の筋肉が硬くなり収縮してしまうため、巻き肩になりやすくなります。その結果、肩こりや首のこりが起こりやすくなり、頭痛につながることがあります。また、低気圧や天候の変化によって体調に影響が出やすくなることもあります。
さらに、巻き肩が進行すると肩甲骨が外側に開いてしまい、肩甲骨の柔軟性が低下します。そのため、腕が上がりにくくなるといった不調につながる可能性もあります。
症状の現れ方は?

巻き肩とは、肋骨と肩甲骨をつなぐ小胸筋が縮むことで、肩が本来の位置よりも前へ引っ張られてしまう状態を指します。姿勢の乱れが原因と考えられており、特にデスクワークが多い方や、スマートフォンを前かがみの姿勢で見る習慣のある方、横向きで寝ることが多い方は巻き肩になりやすい傾向があります。
肩が丸くなり、前方に出てしまうことで猫背にもつながり、背中や腰に負担がかかる可能性があります。
巻き肩が進行すると、呼吸が浅くなりやすく、疲労感が増すことがあります。また、新陳代謝の低下や睡眠の質の低下につながることもあります。
その他の原因は?

姿勢と巻き肩の関係について
筋肉の柔軟性が低下すると、肩甲挙筋や僧帽筋上部繊維の緊張が高まり、肩甲骨が挙がりやすくなります。その結果、肩のこりなどが起こる原因となることがあります。
学生の方の場合、スマートフォンの使用が一因となるだけでなく、勉強中の姿勢によって巻き肩になってしまう可能性があります。
座っているときの姿勢も重要です。椅子に深く腰をかけ、座骨を座面に当てて背筋をまっすぐ伸ばすことが、正しい座り方とされています。座るときにやや前傾姿勢になっていたり、椅子の奥まで深く腰をかけて背もたれに寄りかからず、背筋をまっすぐに保つようにすると、座骨が座面に当たり、自然と骨盤が立った状態になります。このような座り方を意識することで、良い姿勢を保ちやすくなります。
巻き肩を放置するとどうなる?

巻き肩をそのままにしておくと、身体の筋肉バランスの乱れを助長し、それによって肩関節や首の関節に過度な負担がかかることがあります。その結果、関節に変形が起こったり、慢性的な痛みにつながる可能性があります。
筋肉のバランスが崩れることで、身体の機能にも影響が出てしまい、頭痛や首の痛みが慢性化することがあるため、体調面にも悪影響を及ぼすことが考えられます。そのため、日常生活において姿勢に気をつけ、定期的なストレッチを行うことが大切です。
また、肩こりや首のこりが悪化し、慢性的な不調につながることや、筋肉に負担がかかることで血行不良を引き起こす可能性もあります。さらに、胸郭が圧迫されることで呼吸がしづらくなり、猫背の状態が進行するおそれもあります。
当院の施術方法について

当院では、猫背矯正の施術を行っております。
施術の流れとしましては、まず横向きに寝ていただき、「僧帽筋」と呼ばれる筋肉に対してストレッチを行っていきます。次に、「大胸筋」のストレッチを行い、肩を前に引っ張っている筋肉をゆるめていきます。
その後、肩甲骨の可動域を広げるために、肩甲骨の動きに合わせてストレッチを実施します。続けて、肩甲骨の牽引を行い、動かしやすい状態へと導いていきます。
次に、仰向けの姿勢になっていただき、首のストレッチを行いながら、首の柔軟性を高めていきます。
最後に、丸くなった背中をしっかりと胸が開いた姿勢に整えるため、ストレッチを行いながら、首の緊張している部分を指で丁寧にほぐしていきます。
軽減していく上でのポイント

巻き肩の軽減に向けて大切なポイントは、日常生活の中での姿勢への意識です。スマートフォンやパソコンを長時間使用する際には、定期的に背筋を伸ばし、身体をリラックスさせるようにして、背中が丸くならないよう心がけることが大切です。
また、寝るときに横向きになると肩が圧迫され、巻き肩の原因となる可能性があります。そのため、仰向けで寝ることを意識すると良いでしょう。
さらに、良い姿勢を保つためには、正しいフォームでトレーニングを行い、身体をしっかりと鍛えることも効果が期待できます。トレーニングを始める前には、胸まわりのストレッチや、全身の筋肉をやさしくほぐしてから行うことで、より安全に効率よく姿勢の軽減が期待できます。
監修

南流山駅前整骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:宮城県柴田郡柴田町
趣味・特技:旅行、スノボ、カラオケ